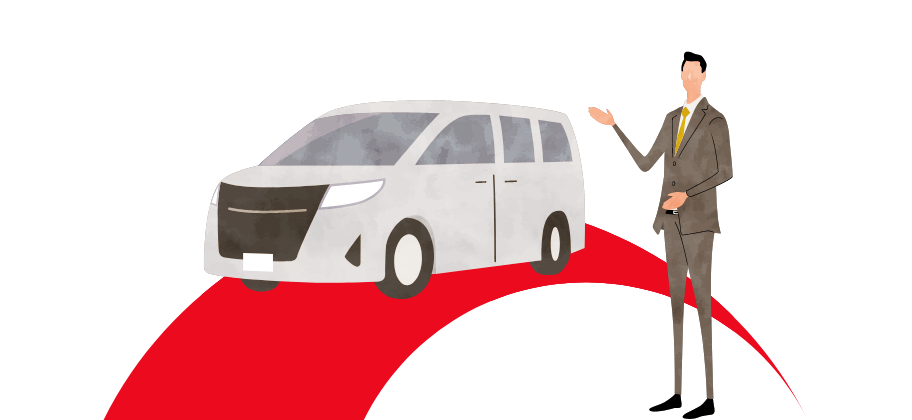MaaS(マース)とは?定義や国内事例から、導入のメリット・デメリットまで解説!

政府が積極的に仕組みの構築に取り組むMaaS。トヨタレンタリースもMaaSに大きく関わっています。
移動の概念を変えるともいわれるMaaSが導入されると、生活にはどのような変化があるのでしょうか。この記事では、MaaSによってメリットや国内外の取り組み事例を解説します。
目次
MaaS(マース)とは

公民連携団体であるMaaSアライアンスによると、MaaS(Mobility as a Service)とは「需要に応じた移動サービスの統合」と定義されています。飛行機や鉄道、バスやタクシーなど、従来は個別に行っていた各交通機関の予約や決済の手間を省き、スマートフォンアプリひとつで出発地から目的地までの最適な交通手段をワンストップで利用できるようにする取り組みです。
MaaSの技術に対しては、単なる交通手段の統合に留まらない効果も期待されています。飲食店やホテルの予約、観光案内や地域イベント情報の提供など、移動に関連するさまざまなサービスと連携して利用者にとっての利便性を高めたり、地域課題や環境問題を解決したりといった効果が考えられます。
MaaSの日本での定義や取り組み
日本では2019年度から各地でMaaSの社会実装に向けた取り組みを推進しています。経済産業省と国土交通省が協働で、地域と企業が手を取り合う挑戦「スマートモビリティチャレンジ」プロジェクトを立ち上げ、全国各地でおこなわれている地域特性に応じた実証実験を支援しています。
政府がスマートモビリティチャレンジの目標として掲げるのは以下の点です。
- 公共交通を便利にして、あらゆる人の移動課題を解決する
- IT(情報技術)を活用して、地域交通の維持と地域の活性化を図る
- 地域と企業を結ぶことで、人流・物流・サービスの円滑化を目指す など
これらに加え、無人バスや自動運転タクシーなどの自動走行技術の発展も、日本でのMaaSの取り組みに含まれます。
MaaSの国内事例
現在日本では、自動車メーカーや鉄道会社など移動体分野に関する企業と通信事業者が主体となり、さまざまなサービスが形になりつつあります。
MSPF(モビリティサービス・プラットフォーム)
トヨタコネクティッド株式会社が構築したMSPF(モビリティサービス・プラットフォーム)は、インターネットに接続された状態で稼働するコネクテッドカーで収集された移動情報などをAPI(ソフトウェアやアプリケーション間で機能や情報を共有するための仕組み)として提供するためのプラットフォームです。
MSPFを通して提供されるデータは直接的にユーザーに関わるものではありませんが、レンタカーやカーシェアの分野におけるMaaSを支える基盤技術として非常に重要な存在です。
アプリサービス「my route(マイルート)」
my route(マイルート)は、トヨタとJR西日本が共同で開発したアプリケーションサービスです。鉄道やバスから、タクシー、レンタカー、自家用車まで、移動に関わるあらゆる交通手段をスマートフォンアプリひとつで検索・予約・決済できるマイルートは、MaaSのわかりやすい形といえます。AIによる最適経路選択により、利用者はもっとも効率的で便利な移動手段を簡単に見つけることができます。
MaaSサプリ「EMot(エモット)」
EMot(エモット)は小田急電鉄が開発したMaaSアプリケーションサービスです。東京・神奈川を中心としたエリアの各公共交通機関やシェアサービスから最適なルートがスマートフォンアプリ内で検索でき、予約・決済も可能です。アプリ自体をフリーパスとして使えるうえ、娯楽施設や飲食店などで使える割引優待などの電子チケットが利用できる点もエモットの特徴となります。
MaaSの歴史と目的
MaaSという言葉がはじめて世に出たのは2012年です。国民に積極的な公共交通機関の利用を促すためのフィンランド政府の取り組みが国際的に注目を集めたことで、世界で認知されるようになりました。
フィンランドでは2016年、首都ヘルシンキの公共交通機関が月額制で利用できるMaaSプラットフォームアプリケーション、Whim(ウィム)をリリース。交通渋滞や環境問題に加え、高齢化によるフィンランド国民の移動問題が解消に向かった実績から、同様の問題を抱える欧米を中心とした各国が追随するようになりました。
MaaSの統合レベル

MaaSの普及にはいくつかの段階が定められています。それぞれのサービスが単体で存在している状態をレベル0として、レベル1〜4の段階でMaaSの普及度合いが表されます。
- レベル1(情報の統合)
目的地までの最適なルートを検索できる段階がレベル1です。交通機関の予約や決済はできないものの、移動経路や利用料金などの統合された情報 - レベル2(予約・決済の統合)
異なる交通機関を組み合わせたルート検索が可能なうえ、予約や決済を単一プラットフォームで行える状態がレベル2です。 - レベル3(サービス提供の統合)
単一のプラットフォームにおいて、各公共交通機関に加えてレンタカーやカーシェアも組み合わせた検索情報が提示された状態や、料金定額制が導入された状態がレベル3となります。 - レベル4(政策の統合)
国や自治体の政策にMaaSが統合され、渋滞抑制や移動の利便性が十分に高められた段階がレベル4です。実現のためには法改正なども必要であり、レベル4に達している国や都市はまだないとされています。
MaaS導入のメリット

MaaSの導入によって生活にはどのようなプラスの影響があるのでしょうか。ここではMaaS導入のメリットを解説します。
交通渋滞の緩和になる
MaaSの大きな特徴は、交通に関わるビッグデータの活用により、目的や距離、時間やコストなどに応じて最適な移動方法が提示されることです。それによって利用されるルートや公共交通機関が分散すれば、交通渋滞は緩和へ向かうことが想定されます。さらに、渋滞が少なくなることで、都市部のタクシーが利用しやすくなる相乗効果も見込めます。
移動手段が便利になる
各公共交通機関の利用料金はMaaSアプリケーションを通してスマートフォンから一括決済できるため、移動にかかる手間を減らせます。さらに、定額制を導入できれば、費用の予測可能性を高め、利用者の経済的負担の軽減にもつながります。運転免許証を返納した高齢者や移動手段が限られる過疎地域においても、買い物や通院といった日々の移動がしやすくなります。
観光客のサポートができる
MaaSアプリケーションにより最適な移動方法とルートを提示できれば、土地勘のない場所や複雑な乗り継ぎが必要な地域でも安心して公共交通機関が利用できるようになります。多言語対応アプリであれば、訪日旅行者であっても容易に目的地までたどり着けるため、これまで交通案内が不十分だった地域へのアクセスが可能になり、さらなるインバウンド観光需要の活性化も期待できます。
物流・運送などのサービスが効率化する
経済産業省では、人流としてのMaaSのほか、運送サービスの効率化を図る物流MaaSも推進しています。物流事業者と交通事業者がデータを共有できれば、交通渋滞を避けた最適なルートでの輸送が可能となります。2023年の法改正で解禁された貨客混載もMaaSの一環であり、過疎地域における物流と旅客輸送を統合することで輸送能力の効率化を見込んでいます。
環境問題への配慮になる
公共交通機関やカーシェアリングなど、自家用車以外の移動方法の利便性が増すことは、大気汚染防止や温室効果ガスの排出量低減にも寄与します。自家用車の数が減れば、空き駐車場などの緑地転用やその他の使い道を見いだすことも可能となるでしょう。MaaSはSDGs(持続可能な開発目標)とも深い関わりがある取り組みといえます。
MaaSのデメリット
メリットばかりに思えるMaaSにもデメリットはあります。
MaaSが世界的に加速すれば、日本の基幹産業である自動車の生産量が減り、国内雇用への影響が懸念されます。また、MaaSのサービス提供にはスマートフォンなどのインターネット接続端末が必要不可欠です。そのため、インターネットを利用できない高齢者などは、どれだけ優れたサービスが提供されてもMaaSの恩恵を受けられない懸念があります。
MaaSの推進には、技術やサービスの普及と平行して、すべての人が公平に利用できる環境の整備も必要といえます。
日本が抱えているMaaSの現状と課題

さまざまなメリットや利便性をもちながらも、MaaSの普及による劇的な生活の変化が感じられない要因には、MaaSの認知レベルの低さに加え、サービス提供エリアが限定的であることが挙げられます。実際、日本におけるMssSの現状はどうなっているのでしょうか。
日本の現状
現在の日本では、官民一体で着々とMaaSの取り組みが進められています。4段階あるMaaSレベルのなかで一部のアプリケーションはレベル2程度に達していますが、国全体でみれば未だレベル1であり、各地方でも実証試験の段階に留まっています。フィンランドのように定額サービスを実現するためには、関連企業間の利害関係や法律をクリアにする必要もあるため、容易に進められないのが現状です。
課題や問題点
現在の日本では、官民一体で着々とMaaSの取り組みが進められています。4段階あるMaaSレベルのなかで一部のアプリケーションはレベル2程度に達していますが、国全体でみれば未だレベル1であり、各地方でも実証試験の段階に留まっています。フィンランドのように定額サービスを実現するためには、関連企業間の利害関係や法律をクリアにする必要もあるため、容易に進められないのが現状です。
法律による問題
各交通機関にはそれぞれ細かな法律による取り決めがあり、本来それらを1つにまとめて運用することは想定されていません。例えば、決済情報や移動情報には個人情報保護法が適用され、各交通機関の予約や決済サービスを提供するには旅行業者としての登録が必要です。
各事業者の価格設定にも法律が複雑に絡み合います。2020年11月に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」が改正されたことで円滑になってはきたものの、画期的な新しいサービスを創出するにはさらなる法改正が必要となり、長い検討の時間を要することになります。
地域ごとに生じる差
地域によって抱える課題が異なる点も障害となっています。最適経路の検索などの機能が組み込まれた都市型MaaSに適合するスマートフォンアプリを交通機関が少ない地域にそのまま導入しても効果は見込めません。
地方でMaaSを推進するには、その土地固有の課題を調査し、住民や自治体の協力を得ながら、それぞれの地域に対応するシステムやサービスを構築することが必須となります。また、それらを企画推進できるリーダーの存在も不可欠です。
データ共有・オープン化
乗客や移動サービスに関する交通データの共有・オープン化は、MaaSの普及において欠かせない要素です。しかし、複数の交通機関やサービスを連携させるには、各事業者が持つ運行データや利用者データを開示することが前提となります。日本は企業間や組織間でのデータ公開に消極的な傾向にあり、この閉鎖的な文化がMaaS導入の妨げにもなっています。
MaaSの今後のさらなる拡大や生活への浸透が期待される
MaaSは、現在はバラバラに運営されている複数の移動体を連携させることで、移動そのものを効率化させる取り組みです。混雑解消や交通弱者対策、環境問題といった多岐にわたる課題解決につながるほか、観光促進や地域活性化といった経済的な効果も期待されています。
MaaSは世界各地で普及が進んでおり、それぞれの生活様式やニーズの変化に応じて、その概念や適用範囲も拡大し続けています。トヨタも、モビリティカンパニーとして日本のMaaSの発展を牽引し、誰もが便利に移動できる新しい社会の実現を目指していきます。
MaaSを推進する、トヨタのカーシェアサービス「TOYOTA SHARE」
トヨタレンタリースが提供するカーシェアサービス「TOYOTA SHARE(トヨタシェア)」も、MaaSを構成する重要なサービスの1つです。
トヨタシェアは、乗り出しから返却までをスマートフォンアプリひとつで済ませられるため、面倒な受付手続きは不要です。月会費無料で最短15分220円から利用可能なうえ、24時間いつでも利用直前の1分前までの予約で利用できます。
トヨタシェアのアプリをスマートフォンにダウンロードしておけば、深夜の用事や早朝の送り迎えなどで急に車が必要になったときにも安心です。ぜひご利用をご検討ください。
\アプリひとつで予約し、お近くのステーションから簡単にご利用可能/
カーシェア