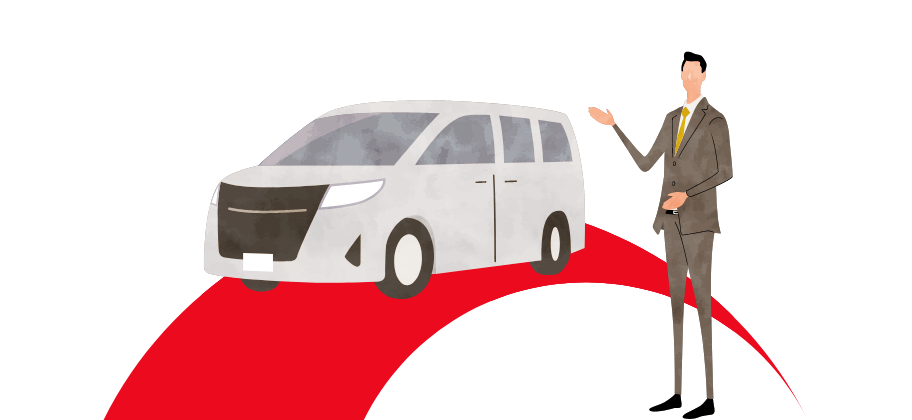社用車の事故時に取るべき対応や事前の防ぎ方を解説!責任は誰がとる?

社用車で事故を起こした場合の責任の所在は事故の状況や就業規則によって異なり、非常に複雑です。また、それに付随して解決すべき多くの問題も発生します。
この記事では、社用車を利用するうえで知っておきたい事故への対処法や保険の適用範囲など、社用車の事故のリスク管理について詳しく説明します。
目次
社用車で事故を起こした際の対応

社用車で事故を起こした際の対応は、社用車を利用する従業員全員に周知しておくべきものです。当たり前のことのように思えますが、対応を誤るとかえって被害を拡大させる恐れがあります。
まずは、社用車で事故を起こした際の正しい対応とその手順を知っておきましょう。
- 安全な場所に車を止める
常に心得ておきたいのは、事故が起きても慌てないことです。パニックに陥り急ブレーキを踏むと、追突されるなどの二次被害に発展する恐れがあります。まずは落ち着いて適切な場所へ安全にクルマを止めることが大切です。ハザードランプを点灯させて停車し、必要に応じて三角停止板や発炎筒を使用して、後続車に危険があることを知らせましょう。高速道路では停止表示器の掲示が義務であるため、車に搭載されていることを確認することも車両管理の範疇です。 - 被害状況の確認をする
運転者には救護義務があります。同乗者や相手に死傷がないかを確認し、負傷者がいる場合は速やかな救護活動が必要です。意識不明などの重傷なら真っ先に119番通報し救急車を手配しましょう。自分もケガを負って動けない場合や、救護で119番通報にまで手が回らない場合は、付近にいる方に手伝ってもらうよう働きかけることも大切です。 - 警察を呼ぶ
運転者には事故の規模に関わらず警察に報告する義務があります。また、警察が発行する交通事故証明がなければ自動車保険は使えません。危険防止の措置や負傷者の救護の手配が終わったら、直ちに110番通報で警察に事故発生時刻と場所、事故の程度と措置内容を伝えましょう。相手の被害が軽度であっても、警察を呼ばずにその場で解決することや独断で示談の念書を交わすことは避け、必ず警察の到着を待つことが鉄則です。 - 相手や目撃者の情報を確認する
相手と会話ができるようなら、相手の住所、氏名、電話番号を確認しておきます。その際は必ず免許証を確認させてもらいましょう。
また、車種やナンバーを車検証と照らし合わせて確認し、事故を起こした状況とあわせてメモをとっておくことも大切です。双方の意見に食い違いがある場合は、周辺の目撃者から話や連絡先を聞いておくことも忘れてはいけません。スマートフォンのメモアプリや録音アプリも活用し、なるべく事細かに記録しておくことが大切です。 - 会社に報告する
会社へのすみやかな報告も必須です。多くの場合、社用車の事故は人事や労務などの部署が処理を担当しますが、まずは直属の上司に報告するのが適切です。 - 保険会社に連絡する
社用車が加入している保険会社へも事故連絡をします。運転者が連絡をするか専門担当者が連絡するかは会社ごとに異なるため、定かでない場合、会社に事故報告する際にどのような対応をとるべきか確認します。会社側がこうした細かな規定を明確にしておくことも大切です。
自己判断での行動はNG!
前述したとおり、警察を呼ばずに双方のやり取りで事故を収めることは絶対に避けるべきです。たとえ相手のケガが軽度で「大丈夫」と言い張ったとしても、後日被害者が被害届を警察に提出すれば、救護義務を怠ったとみなされ、ひき逃げ(救護義務違反)として重い処罰が下される恐れがあります。
また、過度な謝罪は相手に実際の過失割合を誤認させる恐れがあるため要注意です。事故解決の際は、当事者同士や目撃者の証言、ドライブレコーダーなどの状況証拠を加味し、警察や保険会社など第三者の客観的視点で状況を精査してもらう必要があります。
社用車の事故が起きた場合に発生する責任とは

勤務時間中に起きた社用車での事故は、運転者だけでなく社用車を管理する会社側にも責任が生じます。社用車で事故を起こした場合の責任関係についても知っておきましょう。
事故を起こした会社側の責任
たとえ社用車での事故でも、運転者には刑事上、行政上、民事上の3つの責任が生じます。運転者に漏れなく科せられるのは、罰金または懲役などの刑事罰と、運転免許の点数加算などの行政罰です。ただし、民事賠償に関しては、社用車での事故は会社と運転していた従業員の連帯責任となるため、相手方への賠償金は会社が負担しなくてはならず、会社は賠償金として負担した支払いを従業員に要求できます。
車の修理費の負担者は誰になるのか
事故を起こした社用車の修理費は原則として会社が負担することになります。労働基準法第16条には「労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはならない」とあり、社用車で事故を起こした際に従業員が修理費を負担することを就業規則等で定めることはできません。
ただし、禁止されているのは違約金や賠償額を事前に定めておくことであり、賠償金を請求することは禁止されていません。運転者の過失内容に応じた正当な負担割合を社内で検討するのが通例です。
社用車での事故はどんな場面で起きるの?
社用車での事故は業務中と業務時間外に分けられ、そのどちらかによって発生する責任の所在も異なります。
業務中
業務中の事故は会社と運転者の連帯責任です。前述したとおり、刑事上、行政上の処罰は使用者に科せられ、民事上の損害賠償責任については連帯責任となります。
業務時間外
業務時間外の事故も、社用車を使用している以上は原則として会社と運転者の連帯責任となります。ただし、社用車を用いての直行直帰を会社側で容認している場合の事故は業務上の連帯責任となりますが、従業員が無断で社用車を使用した場合や、通勤や帰宅ルートを大きく外れた私用中の事故については業務の範疇と見なされず、運転者の責任となるのが一般的です。
保険の適用について
社用車での事故による賠償は、多くの場合、会社が加入している自動車任意保険の保険金から支払われます。ただし、マイカーを業務に使用していた場合は社用車の保険は適用されないため、運転者がマイカーにかけている保険を使わざるを得なくなります。
また、業務時間外の社用車の無断使用時などに起きた事故は運転者が全責任を負うことになりますが、運転者がドライバー保険や他車運転特約等に加入していれば、運転者が加入している保険が適用されます。
社用車での事故を予防するためには?

- 定期的な交通安全研修の実施
事故予防には、交通安全研修などを実施して安全運転を意識づけることが効果的です。自動車学校などでは企業向けの交通安全運転講習やドライビングレッスンなどがおこなわれています。車を運転する業務に従事する従業員全員を定期的に講習会に参加させることで、安全意識の向上と継続が図れます。 - 社用車の管理・メンテナンスの徹底
故障等の車両トラブルが事故に発展するケースは珍しくありません。事故責任の所在を明確にするためにも、日常点検の実施に加え、不具合が起こらないよう整備を入念に実施することが大切です。
エンジンオイル交換やタイヤ交換などの費用が含まれたカーリースで社用車を契約すれば、整備スケジュール等の管理をリース会社に委託できるため、車両管理の手間を省けるほか、つねに適切な状態で社用車が使えるようになります。 - 運転支援システム搭載車の導入
衝突や誤発進、車線逸脱などを防止する安全装置が備わった車を社用車として導入すれば、ヒューマンエラーによる事故は高い確率で減らすことが可能です。このような先進安全装備は絶え間なく技術が進化するため、ほんの数年で性能が大きく向上します。カーリースなら、頭金などの初期費用がかからず乗り換えができるため、常に最新の安全装備を搭載した車両を乗り継ぐことができます。 - 従業員の体調確認
事故を防ぐためには従業員の体調管理も欠かせません。アルコールチェックを含む健康状態の記録の実施はもちろん、業務内容に無理がないかを精査したり、顔色は悪くないかなど従業員の様子を注視したりしておくことも事故防止につながります。
社用車事故に関してのQ&A
Q 事故を起こしたら会社でのペナルティがある?
社用車で事故を起こした際に従業員に与えられる罰則があるかどうかは、会社の就業規則や車両管理規程などによります。また、降格や減給などの処分の規定内容は労働基準法に従う必要があり、細かなルールが定められています。こうした規定を設けた場合は、就業規則や車両管理規程での周知が必須です。
Q 通勤途中に事故を起こしてしまった場合はどうなる?
社用車を使用しての通勤や帰宅中であっても、運転中の携帯電話の使用などのながら運転や飲酒運転など、事故原因が従業員の重大な過失によるものであった場合は、解雇もあり得ます。具体的なペナルティについては会社ごとに異なり、労働災害に該当するかどうかによっても大きく変わります。
Q 保険で支払われる範囲は?
自動車任意保険で賠償されるのは以下の範囲です。ただし実際に賠償される範囲は、契約を交わしている内容のみに限られます。支払われる保険金額についても契約内容や損害額、双方の過失割合などに応じて変動します。
- 相手方の死亡保険金やケガに対する治療費・通院費・看護費・慰謝料・休業損害などの賠償
- 相手方の車両や物に対する賠償
- 同乗者を含む自方の死亡保険金およびケガの治療費・休業損害に対する補償
- 車両保険に加入している場合は、自方の車両修理費用の補償
社用車の事故による責任を理解して、事前に防ぐための対策を万全にしよう
責任関係が複雑な社用車の取り扱い。事故が起きた際は適切な対応が必要ですが、何より大切なのは事故を未然に防ぐ仕組みづくりです。ドライバーへの教育や車両管理の徹底など、事故リスクを引き下げる取り組みを多面的に取り入れましょう。
事故防止において、最も即効性が高いのはテクノロジーの活用です。その中でも、運転支援システムを搭載した車両の導入は効果的な手段の一つと言えるでしょう。
トヨタでは、運転補助システム「Toyota Safety Sense」などを搭載した車両を提供しています。これにより、事故のリスクを大幅に減らし、より安全な運転をサポートします。例えば、衝突回避支援システムや車線逸脱警報には、先進技術が搭載されていることで運転手の負担を軽減します。このようにトヨタレンタリース神奈川では、安全機能を備えた車両を取り扱っており、安心して利用できる環境が整っているほか、万が一の事故の際もサポートが充実しています。
社用車のサポートを充実させたいとお考えの企業様は、ぜひトヨタレンタリース神奈川までお気軽にご相談ください。
\社用車の導入・乗り換えをお考えの方はこちら/
法人お問い合わせ